
今朝のYahoo!ニュースで、文部科学省が進める「特定分野に特異な才能のある児童生徒」に対する教育支援が取りあげられていました。
「特定分野に特異な才能のある児童生徒」とは、定義を見るとギフテッドとほぼ同じですが、日本では「ギフテッド」という呼び方はしないようですね。
「ギフテッド」という言葉には、何か価値判断のようなものが含まれてしまうからでしょうか?
それとも、さまざまなイメージが先行している言葉なので、誤解を避けるためでしょうか。
それとも、単に外来語だから?
ともあれ、「特定分野に特異な才能のある児童生徒」は長くて難しい名称なので、このブログでは今後も変わらず「ギフテッド」と呼ぶことにしますね。
記事の中で、愛媛大学教育学部附属才能教育センター長の隅田学氏が次のように話していらして、私もたいへん共感しました。
文科省の有識者会議は、「児童生徒を特定の基準で選抜し、特別なプログラム等を提供することを目指すのではなく、才能のある児童生徒を含むすべての子どもたちが多様性を認め合い、高め合える指導・支援の在り方を考えていくこと」を基本的な考え方としています。
愛媛大学では2010年から、興味関心や能力の高い幼年期の子ども向けの教育支援活動「キッズアカデミア」を実施しているそうですが、地域を超えてさまざまな才能を持つ子どもたちが参加しているようです。
真偽のほどは不明ですが、今の現状では、ギフテッドの子どもたちは海外の教育施設に入学する傾向があると聞いたことがあります。
これからの日本の発展のためにも、ギフテッドの才能を活かし育てる努力は、とても大切なことではないかと思います。
せっかくの才能を隠したりせずに、生き生きと学べる教育環境が整備されるといいですね。
ちなみに、私が住んでいる高知県では、昨年12月に、全国に先駆けて「日本ギフテッド・2E学会キックオフ大会」が開催されました。
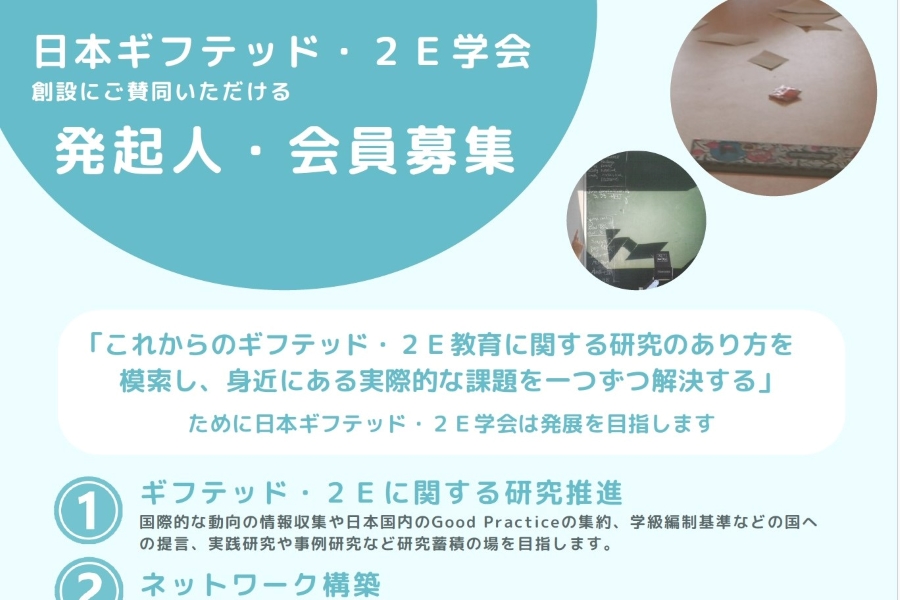
身近な地域からギフテッド支援の輪が広がっていくことは、とても嬉しくて楽しみなことです♪
取り急ぎ、ご報告でした!
最新ニュース・関連情報はこちら↓
さらに詳しく「IQ133(ギリギリギフテッド)の子どもたちの学習・生活の実態」を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください:
“ちょっと賢い”だけじゃない、ギフテッドのリアル
ゲンコツよりタイクツが辛かった話
書くことをやめてしまった日


コメント